聴覚の偏り
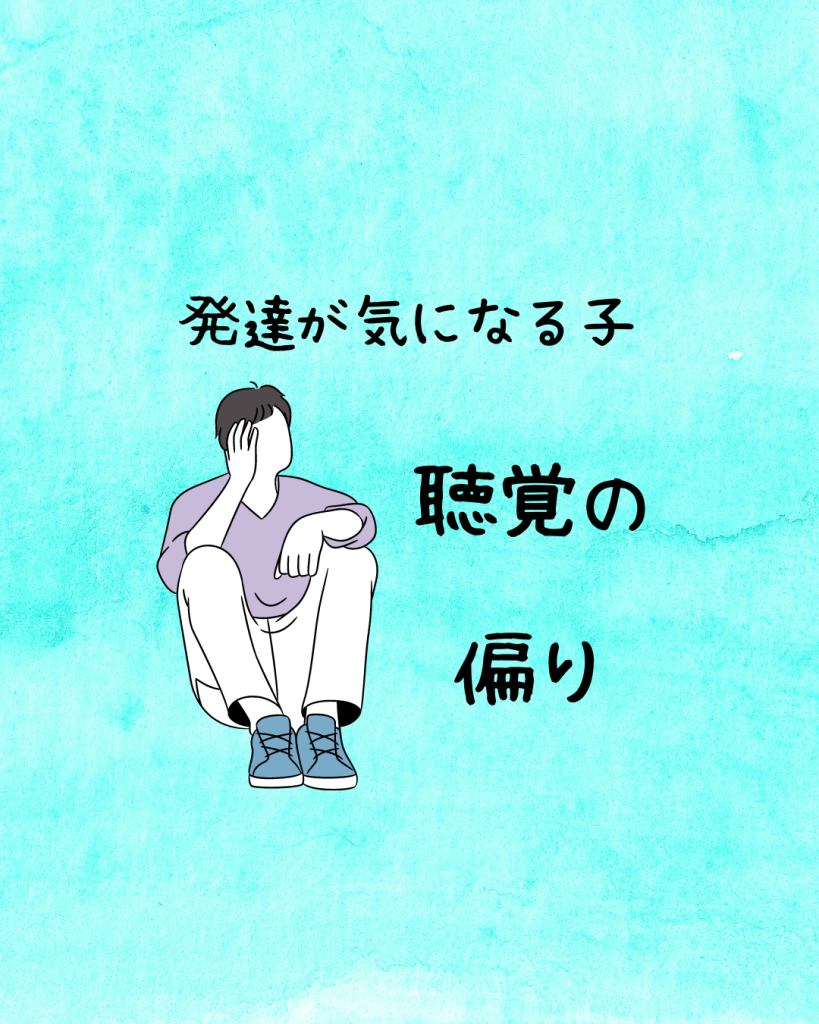
聴覚の偏り
こんにちは!今日は感覚の偏りについての続編「聴覚の偏り」をテーマに解説していきます。
感覚に偏りがあるとはどういうことなのか?どのような支援が必要なのか?
最後まで読んでいただけると幸いです♪
それでは、スタート♪
こんな姿みたことないですか?
はじめに、運動会などで、大きなBGMや声援、ピストルの音に耳をふさいで固まってしまう子を見たことはありませんか?
これは、聴覚過敏の子に見られる姿です。
彼らは耳を塞ぐことで自分の安全を守っているのですが、周囲からはなかなか理解されず、
集団に入るように促されたり、手を解かれたりと苦しい思いをすることが多くあります。
では、聴覚過敏にはどのようなことがあるのでしょうか?
聴覚の偏り
はじめに、感覚の偏りには敏感と鈍麻がありますが、聴覚の場合は過敏が多いように思います。
聴覚過敏の特徴はこんなことがあります。
音の区別ができない
まず、私達は無意識の内に、数ある音声情報から必要な音のみを選択して認識することができます。
ですが、聴覚過敏があると、全ての音が同じ音量で認識されてしまいます。
外にいると、車の音やBGM,人の話し声など、様々な音で溢れていますが、それらが全て同じように頭に入ってくるということです。
学習面でも、先生の話しに集中しなければいけないのに、ペンの音や教科書をめくる音、椅子を引く音など様々な環境音が同じ音量で入ってくるので、集中できません。
音が刺激になる
次に、音が全て同じ音量で入ってくることに苦手・不快と感じるだけでなく、その音がドリルのように刺さり、痛みすら感じる人もいます。
聴覚の偏りの要因になる音
そして、音の刺激が特定のものにあることも。
例えば、掃除機の音、人の声、車の音、などが苦手な人もいます。
その他に、予期せぬ音への恐怖や不安を感じる人もいます。
聴覚の偏りへの支援
では、そのような特性をもつ場合への支援はどのようにしたらいいでしょう?
感覚の偏りに共通して言えることは、努力では解決しないということです。
つまり、解決していくためには、その刺激を取り除くことしかできません。
学習面でも力は十分に持っているのに、環境が刺激になって集中できないことで発揮できないということも多くあります。
ですから、個別での学習時間を設けるとか、クールダウンの部屋を用意するなどの工夫が必要です。
イヤーマフをするのは音の刺激を抑えることが目的です。
つまり、冒頭の耳を塞ぐということも、自分にとっての防御であるわけですから、むやみに手を引き剥がしてはいけません。
感覚の偏りへの理解
最後に、聴覚過敏はめまいや頭痛などの心身の状態にも影響を及ぼすことがあります。
ですが、なかなか理解を得にくいという特徴もあるのが実際のところです。
聴覚過敏に限らず、人と少し違うところ、特性と呼ばれることに対して
異質なものと捉えるのではなく、当事者の思いに立って、寄り添うことが何よりも大切な支援になります。
ということで、本日は聴覚の偏りについて解説してきました!
次回はまた別の感覚の偏りについて取り扱いたいと思います♪
前回の視覚の偏りについてはこちらからもごらんいただけます♪

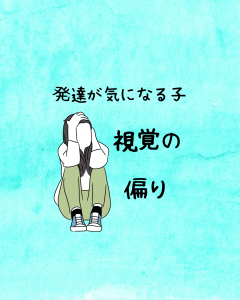
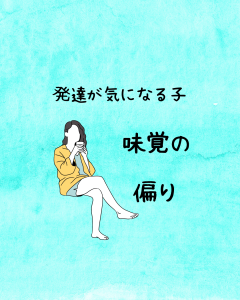
“聴覚の偏り” に対して1件のコメントがあります。